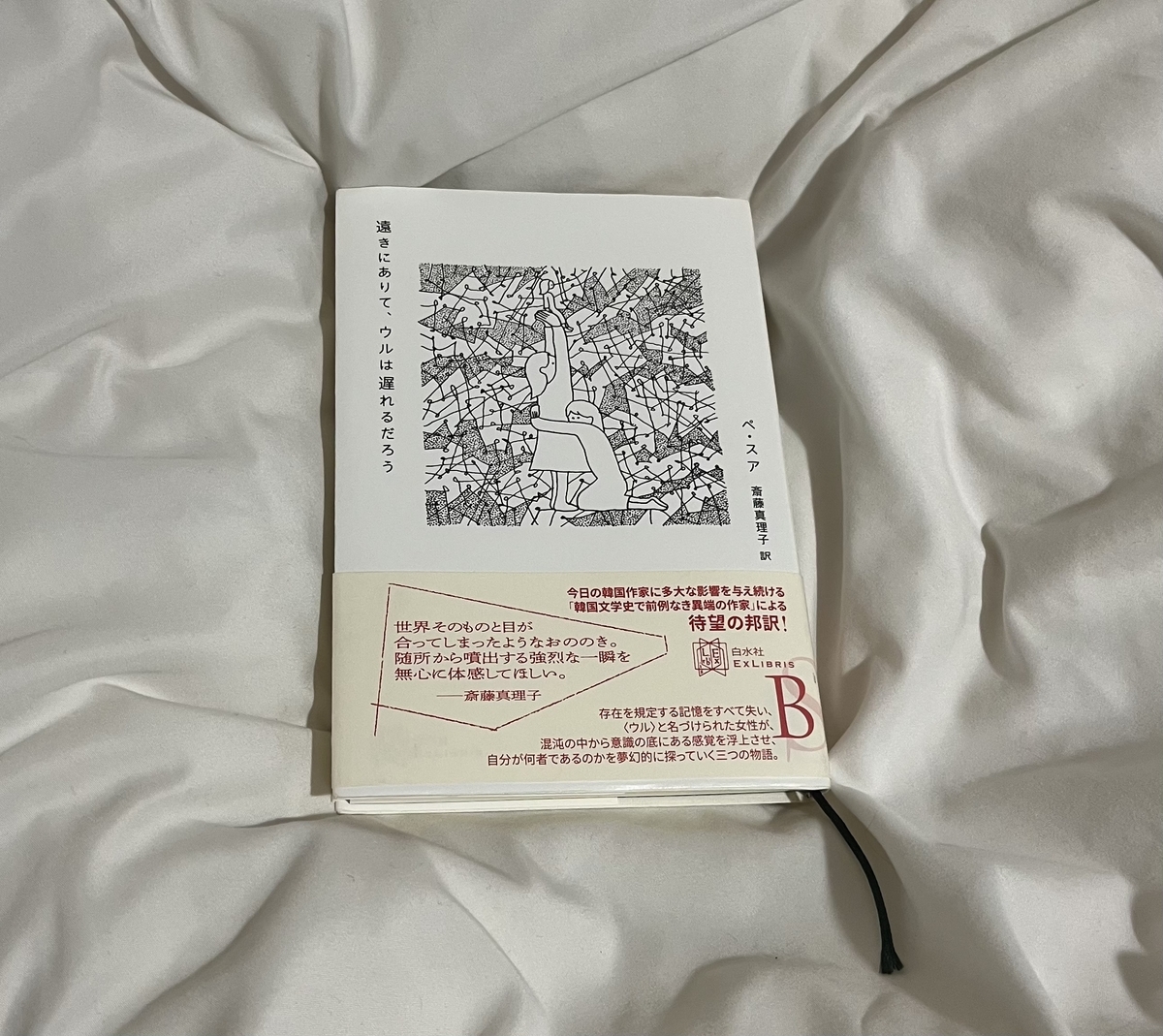3月29日、金曜日。年度末、最後の日。三月が終わる。わたしの二年目が終わる。ベランダに出て、遠いビルの明かりを見つめながら、煙草を吸う。ちょうど最後の一本だった。終わった。ちゃんと終わった。終わって本当に良かった、という実感を噛み締めている。
大学を卒業して、この仕事を始めてから、丸二年が経った。やっと、二年が終わった。この二年という年月はわたしのこれまでの人生のどのときにもなかった類いの二年だった。思い返したときに、過ぎ去るまでが早かった、とも、もっと長く感じた、とも違う実感がある。ただ、重たく、濃密で、激しく、嵐の後の激流に揉まれ続けるような時間だった。
二年前、わたしは、社会のことをなんにも知らないまま、学校社会以外の、もっと広く、よりさまざまな秩序が入り乱れる、多様で乱暴な社会に呑まれた。それまでにわたしのいた学校という小さな社会があまりにも限られていて、やさしかったというのが正しいのかもしれない。大学では社会学を学んでいたし、アルバイトもたくさんしていたし、ボランティアもしていたし、いろんなひとと出会ったし、その分嫌なことも辛いこともたくさん経験した。だから、それなりに社会というものを知っていると勘違いしていた。(わたしが選んだこの仕事が、少し特殊だったことはあるかもしれない。どこかの就職サイトにあったきつい営業職ランキングなるもので、不動産と生保に続いて3位だったのを見たことがある。)だから、一年目は衝撃的だった。何度も強く頭を殴られたような気持ちになった。その傷を癒して自分の中で消化する間もなくまた殴られて、それを繰り返すうちに一年目の秋の終わり、冬が始まるころに精神がだめになった。休職という、虚しく苦痛な時間を過ごしながら一生懸命休み、そうして復職して、また一年を走ってきた。
正社員で週に五日働くということは、五日間のリズムの中で休まず回り続けなければいけないということだった。悲しいことがあっても苦しいことがあっても、次の日はやってくるし、出勤の時間はやってくるし、仕事という流れのスピードは決して緩まない。もちろん体調が悪ければ休むし、動けなければ休むし、有休も取れる。わたしの会社は労働条件は普通にちゃんとしている方だと思う。でも、そういうことではない。どんなにきつくても、それこそ休職でもしない限り、この週に五日のサイクルとそのリズムは延々と続く。わたしは、その中で、自分をハンドルできるできないに関わらず、延々と回り続けなければならない。そういう働き方を選んだのだ、と思った。それは、少し愕然としてしまうぐらいの、イメージのギャップだった。
二年目は、一年目の最悪さよりはマシだった。でも、マシだった、くらい。耐え難いほどにつらく、もう続けられない、と思う夜も数えきれないほどにあったし、休職こそしなかったけれど、二、三日動けない状態になる時期が二ヶ月に一度くらいの頻度でやってきた。ただ、より適応できるようにはなってきたと思う。クレームの処理を一人でやって、普通にお昼も夜もご飯を食べられたときは、タフになってきたな、と思った。一年目の配属当時、上司に、個人的な感情は切り離そうね、とよく言われた。クライアント、カスタマー、どちらにも感情移入してしまうわたしにはそれがとても難しかった。むしろ、その共感力が自分の強みだったのに、この仕事では、それはほどほどに持つべきもので、優先すると自分が潰れる。だから、感情を割り切り、鈍く鈍くいられるように努力した。でも、そう努めることは、この仕事で生きていくためには仕方がなかったけれど、多分、わたしの本意ではなかった。
利益追求のビジネスにおいては、それがどんな業種であれ、利益のための合理性が求められる。その中で、個人感情を優先的に考慮することが必ずしも正しいとは思わない。その必要性は理解しているけれども、あまりにも生身の人間と近いところにあるこの仕事において、感情を一旦横に置いてビジネスの合理性を優先しなければならないことは、度々わたしにとってはつらいことだった。
回数を重ねれば、慣れれば、できないことはない。そういう意味でも、そこそこにうまくやれるようにはなってきた。でも、本意ではない、望んでいない、という違和感が拭えないまま、三年目を迎えることになった。
大学の頃に友人たちと、「幸福論」というテーマでフリーペーパーを作った。(当時、フリーペーパーを作成・配布するサークルに所属していて、それは卒業前の最後の一冊だった。)その際に、インタビュー企画でテーマについてインタビューをしたとある企業のCEOの方が言っていた、いまだに忘れられない言葉がある。
〈働き方のバージョン1.0は生存のため、2.0はお金、3.0は自己実現のためなんですよ。そのバージョンが高ければ高いほど幸福度が高いと思います。(略)別にやりたくないけどやらなければいけないことを一日の三分の一できますか、ということです。私は、かなり無理があると思って。だから、自分の幸福と仕事は結びつけてしまった方が早いというか、より幸せには近道かな、と思っています。〉
当時、就職活動を始めたばかりだったわたしには、この言葉たちが印象深く残って、この話を軸に今の仕事を選んだ。やりがいがある、自分の信念や幸福と結びつくような仕事を選んだつもりだった。しかし、実際に仕事というものを始めてみて、一日の三分の一以上の時間を費やしてみて、これはそう容易いことではないと知った。さらに時間が経った今は、言葉通りのシンプルな話ではないということをなんとなく理解してきた。恐らく、苦しいことがない仕事もつらいことがない仕事もない。365日ずっと楽しいこともない。幸福であるということは、幸せだ、と毎日感じ続けることというよりかは、もっと、過去と現在と未来の全体を見た総合評価の結果のような気がする。そういう意味で、彼女の言った、自分の幸福と結びつく仕事とは、ネガティブな事象に直面しつつも(或いはそれが終わった後にでも)、それでもその仕事を信じられるか、好きだと言えるか、やりがいがあると思えるか、ということなのかもしれないと今は思う。仕事を労働と呼び、やりがいや自身の幸福から切り離されたものと捉える人たちもいる。わたしもそう捉えるべきかと考えることもあるのだけれど、その度にあのインタビューを思い出す。自分が少しでも正しいと信じられる仕事をしたい、と思ってしまう。一方では資本主義を支持できない考えがありながら、矛盾しているとも思うけれども、やはり、自分の生活の一日の三分の一の時間を、心を無にして過ごすことは、多分わたしにはできない。社会を構造ごと変えることはできないけれど、自分の信念に沿った、誰かのためになる仕事をしたい。彼女の言っていることを実現することは理想論に近いかもしれないけれど、わたしなりに納得できる、やりがいを見出せる仕事をしていたい、と思う。
それで言うと今の仕事は、やりがいがないわけではないけれども、苦痛の部分があまりにも自分にとって大きいように感じている。また、こなせないことはないけれども、自分に適性がある方か、と言われると、あまり向いていない方だとも思う。同僚との関係はかなり良好で、それはとても大きな救いだ。上司との関係はイマイチ、他部署の人もいい人が多くはあるけど、社内営業は息苦しいことも多い。この三月に組織改変で最悪なことも起こった。四月から昇進が決まっているけれど、多分、ここではない場所で、次のステージを探すときが来ているだろうなと思う。
何はともあれ、それでもこの二年を走ってこれたこと、本当に良かった、と思う。改めて、何度も、しみじみと思う。学生時代も楽しくて好きだったけれど、わたしはずっと、はやく働いて自分で生計を立てて、自分で自分の人生をちゃんと作れるようになりたかった。あまり折り合いの良くない親から、はやく完全に自立したかった。そう考えると、わたしは長年の願いを叶えることができて、いまを生きている。そして、毎日、やっとの思いではあるけれど、なんとか仕事に行くことができる健康な身体がある。生活できるだけのお金を自分で稼ぐことができている。それは既にとても幸福なことであるとも思う。
三月は去る。そうして一年一年が、毎度ちゃんと終わることに心から安堵する。良かった思い出も苦しかった記憶も全部置いて、新しい四月で生まれなおすことができますように。願わくば、三年目のその道があまり険しくなく、わたしにやさしくありますように。